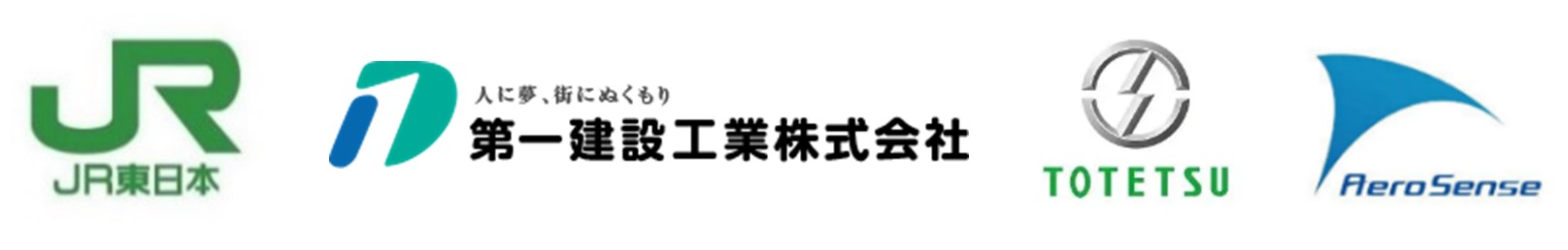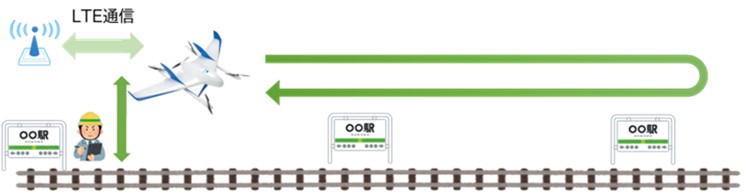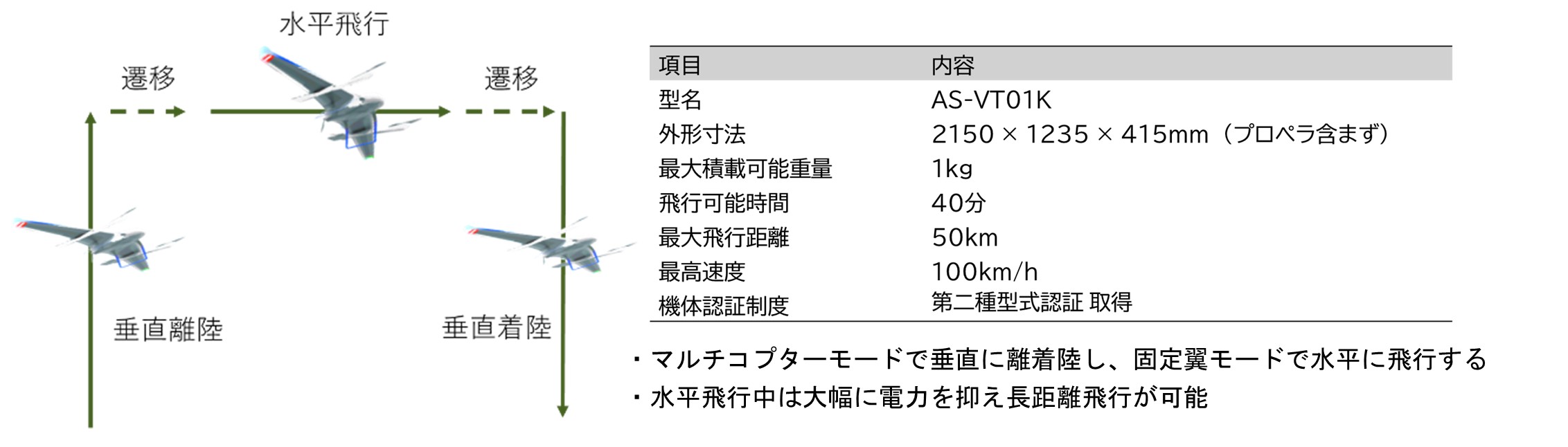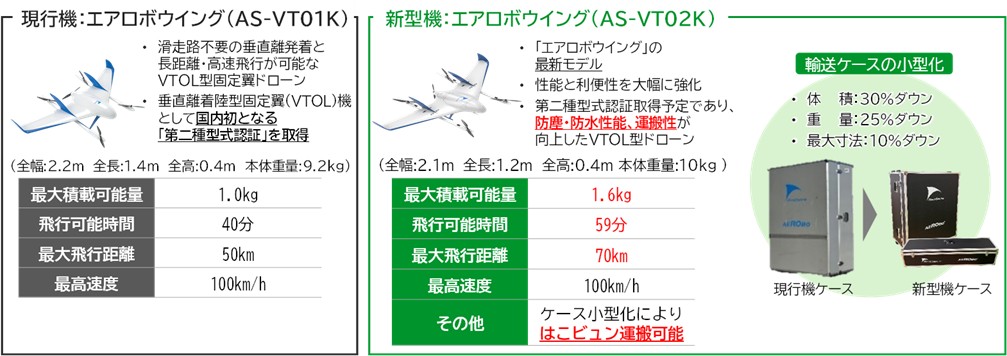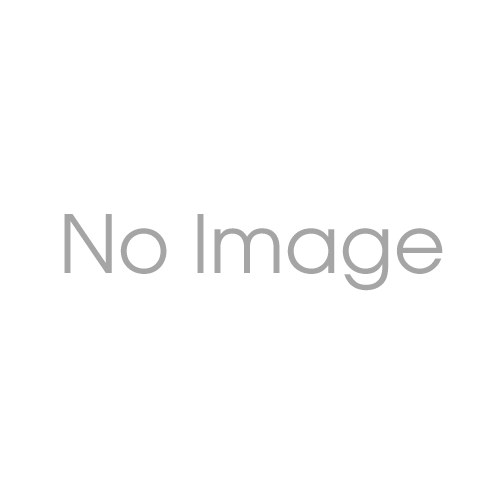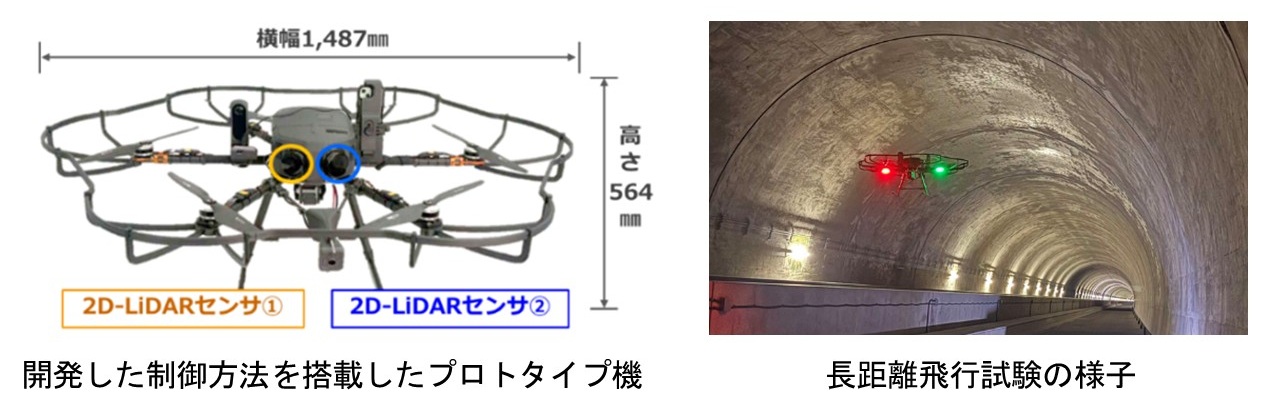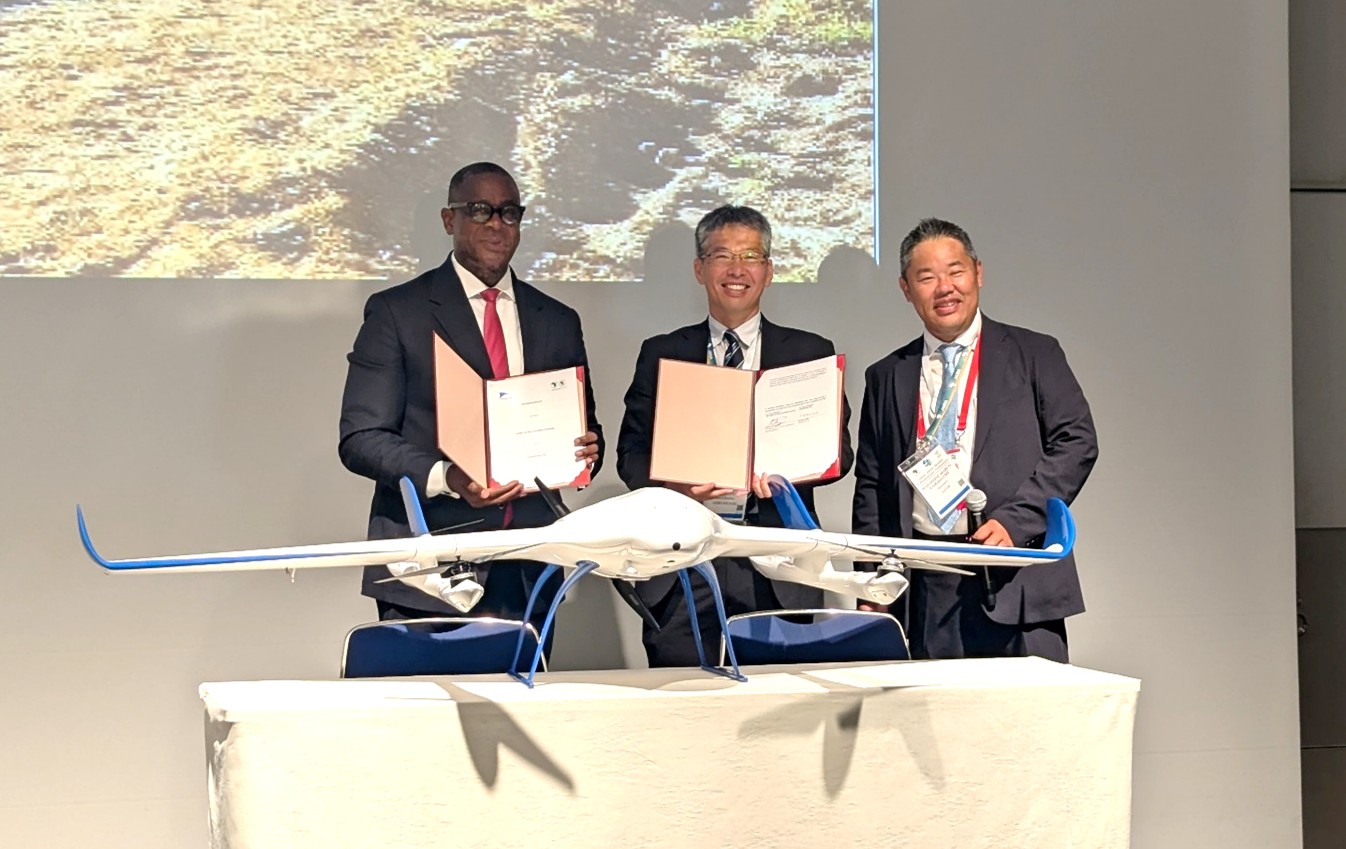年末年始の休業のご案内(2025/12/27〜2026/1/4)
日頃より弊社ウェブサイトをご利用いただきありがとうございます。
誠に勝手ながら、弊社では下記の期間を年末年始休業期間といたします。
2025年12月27日(土)〜2026年1月4日(日)
※12月27日中にいただいたお問い合わせは、年明けの回答となる可能性がございます。予めご了承ください。
休業期間中のお問い合わせには、1月5日(月)より順次回答いたします。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
エアロセンス株式会社